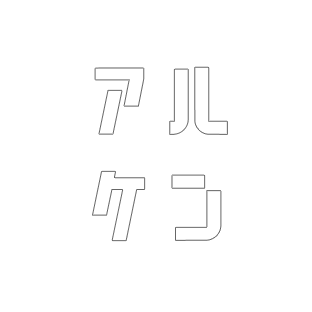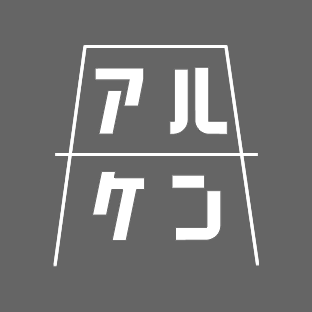青木 淳
聞き手 畔柳 昭雄
住宅から店舗、公共建築まで幅広い分野で建築界の第一線を走る青木淳さん。
その独自の作風は、他の追随を許しません。今回はルイ・ヴィトンの仕事などを中心に、素材と設計手法についてお話を伺いました。
テクスチャーをつくる
― ルイ・ヴィトン香港ランドマーク店ではルーバーにアルミを使っていますね。
9ミリ厚のアルミです。ブレードの小口と側面の仕上げをそれぞれ別に扱って4種類の組み合わせとし、全体としてダミエ・モチーフ(ルイ・ヴィトンの代表的モチーフの1つ)を浮かび上がらせたかったため、小口が認識できる厚みが必要でした。また、香港の街には独特の強さがありますので、ルーバー自体に〝ごつい〞という感じがほしかったということもあります。いろいろ試してみましたが、9ミリくらいないとあの街に合う物質感にならないと感じました。
― スタディをするときには、やはり相当数模型をつくるのですか?
この建物の場合だと、200分の1から始めました。しかし、そのスケールではルーバーをつくることができませんから、イメージに抽象化した模型ということになりますね。それから、模型のスケールをだんだん大きくしていき、最初のイメージどおりになり得るかどうか判断します。大きくなるに従って現実的になり、夢が崩れていきがちですが、それを崩さずに、どうしたら最初の雰囲気を保てるかに気を遣って、スケールアップをしていきます。
― モックアップなどで検討しないと、最初のイメージに行き着かないのではないでしょう
そうです。ルイ・ヴィトンの仕事の多くは、その造形性が主題というより、モノのテクスチャーが重視されています。テクスチャーですから、実際につくってみないとわかりません。5分の1くらいまで事務所でつくり、そこでうまくいくようであれば原寸モックアップで試します。
― アルミでない素材の可能性もあったのですか。
エッジのシャープさという点から金属の無垢材でつくりたいという思いがありましたし、かつ重量の問題からアルミ以外では考えられませんでした。しかし、要望する加工ができるところが少なく、結局オーストリアでつくることになりました。白く塗ってしまう部分が多く、アルミの素地が出る部分はほんのわずかなのですが、そのほんの少しの部分で見え方がまったく違ってきますから素材の選択は重要です。
― 窓の位置なども、そうとうスタディをして位置を決めていますよね。
事務所を始めたころは、求められている機能を、常識にとらわれず、今までなかった別の空間構成でかなえることができないか、というようなことを考えていて、結果、アクロバティックな空間構成の建物をつくることになりました。でも、そうしていると、新しい空間の構成さえできれば、それだけでもう新しい建築になっているような錯覚に陥ってしまい、素材なんてどうでもよくなってしまいますね。しかも、常識をうまく越えたところで、その新たな構成もまた新たな常識になってしまうかもしれず、どうも違うなあ、と思うようになりました。それで、どんどん一見、普通の建物になっていきました。ルイ・ヴィトン名古屋栄店などでも、使いやすいのは四角い空間なのだから、単純な直方体でよいのではないか、と。単純な四角であれば、あとは空間の質を考えるしかありません。そしてそうなってくると、どんな窓でもよいというわけにはいかなくなってきます。窓の位置の最終的な決定ということになると、数多く試してみるということに尽きます。あらかじめ決めるのではなく、いろいろなことをやって、うまくいきそうな落ち着きどころを探していくという地道なことの繰り返しですね。
物質に見えないもの
― テクスチャーをつくるという言葉がありましたが、イメージの源泉は何なのでしょうか。
たいていは、小さい時の経験みたいなものだと思います。小さい時の記憶は明確ではなくて、霞んでいるというか、おぼろげです。蚊帳の中で寝たときの、あのモワァーとした感じとか。そんなかつて実際に自分が体験した感覚をテクスチャーに置き換えようとします。香港ランドマーク店の場合も、ずっと敷地に立って、どんなふうになればよいのかを想像しましたが、その段階ではまだ具体的な材料などありませんでした。でも、あの街のごく普通の集合住宅を外から見ていて、そこから僕のなかに生まれた、言葉にならない、でもある特定の感じを、そこにどう定着できるか、と思ったものです。
― モアレのような目の錯覚を積極的に表現に利用されているのかと思っていましたが、違うのですね。
錯視ということに、興味はありません。モアレの外壁は、ルイ・ヴィトン名古屋栄店で初めて試みた方法ですが、それは素材の素材としての表現を失った、非物質的な様相を見せることがもっとも強い素材だと考え、それを追求した結果、辿り着いた方法だったのです。というのは、どんな外装でも、見る間に、見慣れてしまいます。何度も見ているうちに、僕たちは、本来はその時だけ発している意味をそこから読み取る努力を省略して、目の前のモノから、もう固定化してしまった意味を思い出すだけになってしまうのです。これは、モノにつきまとう宿命のようなもので、ですから、ひとつの意味に収束しない、素材として特定できない、モノとは見えないモノでできていたらなぁ、と思ったのです。つまり物質に見えない方がよい、ということですね。物質でないものというのは、子どもの頃の記憶とか、暑い夏に感じた臭いとかで、そういったモノとしては見えないものであれば飽きられることもないと思ったのです。
― 素材から考えるようになったということでしょうか。
たしかに、素材に対し意識的になったのは、この設計のときからです。その前も素材をどうするか考えるのは好きでしたが、やはりその決定はデザインのなかで最後の作業でした。ルイ・ヴィトンの仕事をすることで、平面計画が最後になったわけではありませんが、素材からも考え始めることができるようになったと思います。でも、僕は素材フェチではないので、特定の素材に思い入れはありません。青森県立美術館では土を大量に使っていますが、それは土が好きだからではなく、土を使ったとしたら何ができるか、考えてみたかったからです。素材は、やはり、デザインの素材です。
― 物質でないものをつくるといったときに、それを通して見る人に何を伝えようとしているのでしょうか。
何かを伝える、ということではないでしょうね。むしろ、ある空間の質をそこにつくりだそうとしているのだと思います。ルイ・ヴィトン香港ランドマーク店のルーバーもそうですが、9ミリ厚のアルミの小口をどうするかで空間は相当違った雰囲気になります。何もしなければただのラワンベニヤのテーブルも、小口だけクロームメッキ処理すると誰もこれをベニヤと思わない豪華さが出ます。小口に高級な材料を高い精度でつけると豪華に見え、逆に高価な素材でも、小口をわざとぺらぺらにすると安っぽく見えてしまいます。青森県立美術館では内装にレンガを用いたのですが、小口でレンガを留めに切っています。45度に切るわけですから小口に線が入り、逆に割れやすくなってしまいます。つまり本物のレンガを使って一番安っぽく見える処理をわざとしているのです。そうすることで、レンガがもっている、ちょっと嫌らしい、スノッブな雰囲気をなくそうとしたのです。素材がもっているさまざまな性質の中でも、ある成分はちょっと強めに扱いたいし、ある成分は弱めにしたいといったことがどうしてもありますので、物質に見えないものをつくるというのは、そういった空間の質の調合作業のことなのです。
人それぞれ感じ方が違う建築を
― 素材を扱う際にはスケールという要素も重要なのではないでしょうか。
自分の設計した建物で特にスケールを意識したのは、たとえば、ルイ・ヴィトン表参道店です。構成する面をなるべく大きい割り付けにし、できたら目地もなくしてしまいたいと思いました。しかし、そんな超越したスケールが可能な素材はあまりなく、最終的に用いたのはステンレス・メッシュでした。短手方向には制約があるものの、巻くことができるので長手はいくらでも長くすることができるからです。スケールを考えることから決まっていった素材ですね。ところで、そのメッシュの素材は、ほかの材料だと性能的に無理があってステンレスに落ち着いたのですが、ステンレスはすぐに光沢を失い、薄汚れた印象を与えてしまいます。それではまずいので、背面に鏡面に磨いたパネルを入れました。背面のパネルは光を受けるので、表と同じぐらいに明るくなるのと同時に、すだれ越しにすだれの裏側が見えるという風情になっています。ですから素材はその組み合わせも重要ですね。
― 同じ素材でも単体と組み合わせるのとでは表情が変わってくるのですね。
たしかにそうですね。ルイ・ヴィトン六本木ヒルズ店では、透明なガラスを組み合わせて白っぽい霧のような、乳白色の白濁した感じをつくろうとしました。ガラスのチューブを用いれば、よりたくさんの光の乱反射が起こり、それが集まれば真っ白になるだろうと考えたのです。そもそもパーティなどで並べるシャンパングラスがヒントになっています。あれはすべて透明できれいですが、並べるとまた違った表情が生まれます。
― 以前、大谷石の採掘現場のお話をされていました。意図してできた空間ではなく、まったく別の意図から偶然できてしまった空間だけれども、そこにはとても強い力があるといったお話でした。そういった空間をつくるということは、設計という行為と矛盾するのではないでしょうか。
たしかに建築にはフレキシブルさが必要ですが、と同時に、普通、建築というのは、相手に何らかの意図を伝えようとしてつくられてきたものです。そこには、伝えようとするものがあります。まず明確に感じてほしいことがあって、それを伝えようとするから強いモノができる。それが、普通の意味で言う、建築における「強い力」です。しかし、僕が望んでいるのは、そういう意味を押し付ける力ではなく、違うタイプの強度なのです。実際、僕は、人それぞれの感じ方は違った方がよいと思っています。感じてほしい方向はありますが、そこに矛盾なり、ブレをつくろうと思います。いや、一度に別々のことを言おうとして、どもってしまう感じなのかもしれません。矛盾もブレも一般的には否定的に扱われます。しかし、街のスピードを考えてみても、一辺倒に、速かったり、のんびりすぎていたりするのはどうかなと思ってしまいます。混在やブレが生じているからこそ豊かなわけです。それらが混ざり中和してしまうと、それはまた魅力的でなくなってしまいます。おのおのの粒がはっきりしながら、かつ混じり合っているというのがよい感じなのだと思うのです。それが、絶対的なブレの、絶対的などもりであり、その強度を高められたらいいな、と思っています。
(青木淳建築計画事務所にて)

-
青木 淳(あおき じゅん)
-
1956年 神奈川県生まれ
1980年 東京大学工学部建築学科卒業
1982年 同大学大学院修士課程修了
1983-90年 磯崎新アトリエ勤務
1991年 青木淳建築計画事務所設立

-
畔柳 昭雄(くろやなぎ あきお)
-
1952年 三重県生まれ
1976年 日本大学理工学部 建築学科卒業
1981年 日本大学大学院博士課程修了
2001年~日本大学理工学部 海洋建築工学科教授