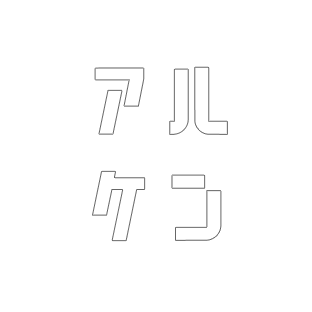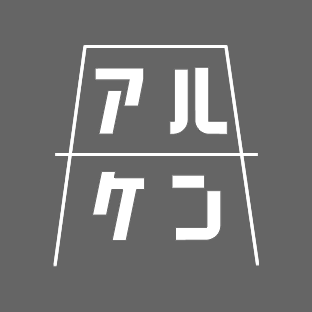隈 研吾
聞き手 畔柳 昭雄
日本はもとより欧米でも高い評価を受け、世界各国から設計の依頼が殺到する建築家・隈研吾。建築家インタビューシリーズ第2回では、隈研吾さんに、「負ける建築」における素材の役割について、最近作であるサントリー美術館などの作品をとおして語っていただきました。
素材から設計を考える
― 隈先生の作品では素材がとても重要な役割を果たしていますが、素材は設計の最初期に決まってしまうものなのですか、それともデザインを練る中で次第にイメージが醸成されていくものなのでしょうか。
一般的に、設計は平面図ありきで、素材は最後に決まります。僕も大組織に所属して設計をしていた頃は、何㎡の部屋がいくつ必要かといった要求に応じて平面図を描くことから始めていました。内外装の仕上げは平面図が決まった後に考えるわけです。要するに素材はお化粧だと言ってよいでしょう。大学における建築教育でも重視されるのは平面計画と形態で、素材に対しては何も教えてくれません。
しかし、そのつくり方には抵抗感がありました。同じ大きさの部屋でも内装が違えばまったく印象が異なります。石でつくる場合と、アルミでつくる場合で部屋の大きさを変えるのは当然ではないでしょうか。
そこで、僕らは、なるべく最初の段階で素材を考えようとしています。素材の違いを意識的に建築に生かすためには、素材を意識しながら設計すべきだからです。とはいっても素材をすぐにイメージするのは難しいことです。また思いついたとしても、なるべく今までとは違ったかたちで素材を使おうと考えますので、なかなかディテールが決まりません。これでいけると思うまでには相当に時間がかかります。SUSさんに協力していただいたウィーザス荻窪にしても、前から気になっていたアルミ押出材を外装に使おうという気持ちは最初からありましたが、ディテールが決まり、これで絶対にいけると実感できたのは設計も半ばにさしかかった頃でした。
― サントリー美術館では白磁や桐、梅窓院ではアルミ、村井正誠記念美術館では廃材、東京農業大学「食と農」の博物館では白河石、広重美術館では八溝杉などさまざまな材料を使用していますが、素材はどのような理由で決まってくるのですか。
敷地の状況や、用途などから決まってきます。ただ、用途といっても単純に学校というようなことではなく、校風とか校長先生の個性とか、教育方針やどのような生徒がいるのかといった、その学校がもっている固有性、シンギュラリティと僕は呼んでいますが、これを引き出してきて、素材に翻訳するのです。その意味で建築は一期一会の産物です。その出会いを大切にできれば、そこで生まれた結晶はとても魅力的なものになり、ずっと長い間、人々に愛してもらえると思うのです。
― 素材に関して、どのように研究されているのかお聞かせください。
常日頃、関心を持ってまわりを見ています。現場での打合せや講演会も素材のサーベイの一環で、行く先々、また移動の道すがら、おもしろい素材がないか変わった使われ方をしていないかを探してしまいます。意識的にではなく、無意識にやっていると言ってよいでしょう。見ただけではわからず、調べることもあります。そこで得た情報がすぐに役立つことは希ですが、頭の引き出しにいれておいて、何年か経ってから思い出して採用します。プロジェクトが始まってから情報を集めていてはよいものはできません。
光が素材の本質を引き出す
― 最近は、さまざまな素材を用いたルーバーにこだわられているように感じます。光に対する意識が背後にあるのではないかと考えているのですが、いかがでしょうか。
素材と光には密接な関係があります。単にコンクリート壁の表面に素材が貼ってあるだけではおもしろくありませんが、ルーバーのように素材の隙間から光が入るようにすると、化粧では絶対に出せない素材の本質が見えてきます。光によって素材の奥行きを表現するディテールをいつも考えています。
― 光の扱いに安藤忠雄さんなどとは明らかに違うものを感じます。
安藤さんの光は、幾何学形態の美しさを際立たせる光です。しかし、現実的には、法的な規制や建主の要求、コストの規制などがあり、幾何学的に美しい建築など簡単にはできません。そこで、重要になってくるのが、素材であり、それを引き立たせてくれる光です。形態がどうであれ、素材をうまく扱うことで魅力的な空間を創造することができるのです。このことは僕が「負ける建築」と言っていることと共通します。たとえ条件に負けても、建築に力をもたせることができるのは、素材と光なのです。
― 昨日、改めてサントリー美術館を拝見させていただきましたが、とても繊細な表現だと感じました。どのようなお気持ちで設計に取り組まれたのですか。
サントリー美術館は「生活の中の美」というテーマでコレクションの収集をしています。つまり観賞のために生まれた美術ではなく、生活の中で実際に使われてきたものを集めているのです。僕は、日本美術の特徴を日常の生活の中に美があった点ととらえています。建築に対しても、特別にお金をかけたものではなく、当たり前の空間の中に気品のあるものをつくりたいと思っています。その意味で、僕の指向性とサントリー美術館のコレクションがぴったり合いました。
― その出会いの中で桐という素材が出てきたわけですね。
桐は弱くて傷がつきやすいといった欠点もありますが、桐タンスのように中のものを大切にするといったイメージもあります。この点をサントリー美術館の人たちが理解してくれて採用に至りました。
― 外壁には白磁を使われていますが、設計の初期段階からイメージとしてあったのですか?
白い陶器の肌を表現してみたいという気持ちは、初めからありました。しかし、レンゾ・ピアノがベルリンでやっている事例を見てもわかるとおり、そのまま使うと、ぽてっとしてしまいます。どうしたらシャープなものができるか悩んだ結果、今回は陶器とアルミを組み合わせることにしました。アルミと陶器の溶接や膨張率の違いなど解決すべき問題は数多くありましたが、結果、シャープなルーバーができたと思っています。かねてからの思いがここでやっと実現しました。「素材は1日にして成らず」ですね。
線の細やかさが気持ちを表す
― ルーバーによって光の本質を引き出すというお話がありましたが、それとは別にルーバーの線が織りなす表現にもあるこだわりがあるように感じられます。
線は人の気持ちを表します。線の細やかさによって、「丹精を込める」といった感情を建築に表現してあげれば、使う人もきっと大切に扱うと思うのです。
その建物を使う人たちをどういう気持ちにさせるかは、平面図で決まるわけではなくて、壁の持っている質感であるとか、その壁を構成する線の太さで決まるのです。設計の際には、人と建築のコミュニケーションに必要なものは何なのかについて熟慮しなくてはなりません。
― 美しい、あるいは効果的なルーバーの寸法はあるのでしょうか。
ルーバーを見て、しっくりこない時があります。その理由を考えてみると、先端の見付の太さに問題があることがわかります。太いとまずだめですね。ONE表参道のルーバーは、集成材ですから薄くすることに限界があるので、先端にカーブをつけています。曲面を使うとある程度太さがあっても繊細さを表現できるのです。実際には、実物大の模型をつくって曲率や羽の間隔などを検討しています。効率の悪い作業ですが、見比べないとなかなか判断できません。
サントリー美術館の無双格子やロータスハウスのトラバーチンでは、面の大きさと奥行き(薄さ)のバランスに神経を注ぎました。トラバーチンは西洋的な色彩の強い石材ですが、薄くスライスして使ったことで、組積造のイメージとはまったく異なる日本的な表現になりました。キーワードはやはり細さ、薄さだと思います。
桐のもつ繊細さをアルミで表現
― 今までウィーザス荻窪のほか、ADK松竹スクエアや梅窓院でもアルミルーバーを使われていますが、今後、アルミをどのように使っていきたいとお考えですか。
アルミは軽く傷つきやすいという点で桐に似ていますので、建築がこれまで桐によって表現していた部分をアルミに置き換えて表現できないかと考えています。つまり「はかなさ」「繊細さ」のようなものをアルミで表現するのです。
意外に思われるかもしれませんが、近代数奇屋を確立した吉田五十八はアルミをよく使っています。吉田五十八はアルミがつくり出す日本的な表現に気づいていた希な人で、彼もアルミと桐の相似性に気づいていたのではないでしょうか。吉田五十八の試みを、もう少し現代的な枠組みの中で表現すること、それがアルミの可能性を広げるひとつの手段なのではないかと思っています。
― アルミの特徴を具現化するために、何かほかの利用法は考えられますか?
床にアルミを使いたいと考えています。床は唯一、人が常に直接触れるところですから、床の素材選びは大切な問題なのです。アルミのもつ独特の質感を足の裏で絶えず感じたら、これまでにはない質感の床ができると思います。
また、「夏の間」といったように季節を限定した空間に、アルミは有効です。桂離宮がよい例で、敷地内には茶亭がいくつもありますが、夏を基準としてつくった茶亭では竹を床に使って涼しさを演出するなど、季節にあった材料を選択しています。本来、建物は場所ごと季節ごとに違ったスタイルがあるべきもの。アルミのもつ涼しげなところを利用した夏の間があってもよいのではないでしょうか。季節との関係から建築をつくりあげるのは、本来、日本人がもっとも得意とすることだと思います。
設計意図をデザインに込めることのできる素材という意味で、アルミは大自然の中というより環境を意図的にコントロールすべき都市にこそ相応しいと考えています。

-
隈 研吾
-
1954年 東京都生まれ
1979年 東京大学建築学科大学院修了
1990年 隈研吾建築都市設計事務所設立
現在 東京大学教授
1997年「森舞台/登米市伝統継承館」で日本建築学会賞受賞、その後「水/ガラス」(1995)、「石の美術館」(2000)「馬頭広重美術館」(2000)等の作品に対し、海外からの受賞も数多い。2010年「根津美術館」で毎日芸術賞。近作に浅草文化観光センター(2012)、長岡市役所アオーレ(2012)、「歌舞伎座」(2013)、ブザンソン芸術文化センター(2013)、FRACマルセイユ(2013)などがあるほか、国立競技場の設計にも携わる。
著書に、『自然な建築』(岩波新書 2008)、『小さな建築』(岩波書店 2013)、『日本人はどう住まうべきか?』(養老孟司氏との共著 日経BP社 2012)、『建築家、走る』(新潮社 2013)、『僕の場所』(大和書房 2014)などがある。

-
畔柳 昭雄(くろやなぎ あきお)
-
1952年 三重県生まれ
1976年 日本大学理工学部 建築学科卒業
1981年 日本大学大学院博士課程修了
2001年~日本大学理工学部 海洋建築工学科教授